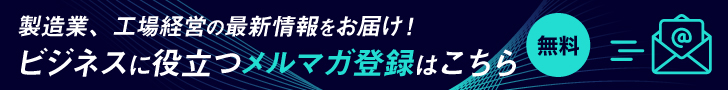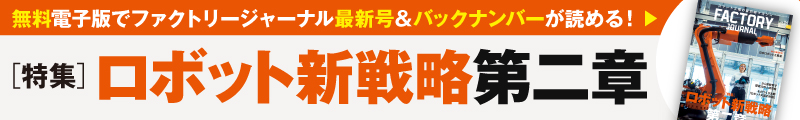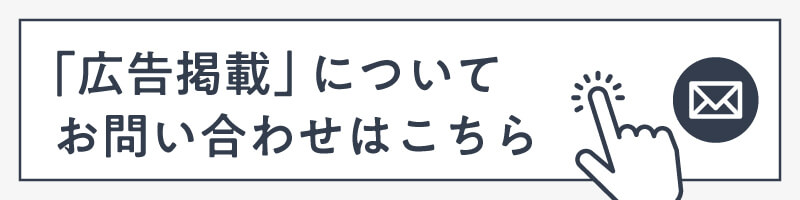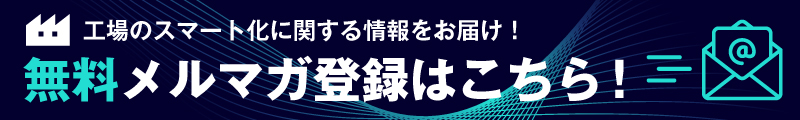【製造業のための脱炭素化入門】取り組みのきっかけは? 課題をどう乗り越えた?
2024/11/05

使用する電気を100%再エネ由来のものにシフトすることを目指す中小企業のイニシアチブ「再エネ100宣言 RE Action(アールイーアクション)」。脱炭素化に奮闘する参加企業のリアルを紹介する。
Case1.木質ボイラーの活用で
取引先から高い評価
ファッション産業の環境負荷、脱炭素化と新規事業で挑む
岐阜県大垣市で染色加工業を営む艶金(つやきん)。洋服に加工される前の布を数十メートル単位で染め、最終的にアパレル企業へ納入する。一反が約40メートルの布の場合、十反を染めるには、約3000リットルの水を使い、布の深部まで染めるために約1時間にわたって加熱するという。「われわれの仕事の最大の特徴は、大量の水とエネルギーを使うことです」と代表取締役の墨勇志氏は話す。
同社は1889年に創業し、1970年代にはオイルショックを経験した。原油価格が高騰し、ボイラーに使用する重油の価格は1年で2倍に跳ね上がった。そのため、木質チップを燃料とするボイラーに切り替えて、経営の安定化を図ったという。現在は、家屋を解体した後の廃材なども利用し、燃料をすべて国内で調達している。
脱炭素化に取り組んだきっかけは、地元の商工会議所から勧められて、CO2排出量を算定する国の補助事業に採択されたことだった。専門家の指導を受けて排出量を算定したところ、木質ボイラーを使用していたため、「ガスボイラーを使った場合と比較して、CO2排出量が約75%少ないという結果になりました」という。
近年、アパレル業界では、取引先などのコンプライアンスの状況を監査する動きが強まっている。海外のアパレルブランドの監査員が艶金の工場を訪れた際、木質ボイラーが監査員の目に留まり、「環境に配慮した取り組みとして高く評価されました」と墨氏は胸を張る。

1987年に導入した木質のバイオマスボイラー。「縁の下の力持ちだったボイラーが脚光を浴びるとは思わなかった」と墨氏は打ち明ける。(画像提供:艶金)
これを機に、艶金の脱炭素化の取り組みは、ファッション産業以外の業界からも注目されるようになった。「世間の関心の高まりが社員のモチベーション向上にもつながっています。ファッション産業は環境への負荷が高いものですが、当社は、ビジネスの力で社会課題の解決に取り組みたいと考えています」。艶金は2008年、食べ物や植物を加工したあとに出る廃棄物を有効活用した「のこり染」という新ブランドを立ち上げた。「脱炭素化や新規事業を通じて、数少ない国内の染色加工業として企業価値を高めていきたいと考えています」と意気込みを語る。

社員の駐車場に、福利厚生を兼ねてカーポートタイプの太陽光パネルを設置。工場で使う電気の数%をまかなっている。(画像提供:艶金)
DATA

株式会社艶金
反物に木槌で艶を出す「艶屋」の墨宇吉翁が1889年に創業。大量生産・大量消費のファッション産業をローカルで循環型のものに戻したいというポリシーのもと、染色加工の技術を通じてメイドインジャパンのものづくりを実現している。
Case2.理念経営へのシフトで
新ビジネスを創出

2030年までに自社の活動によるCO2排出量をゼロにすることを目指している。設備ごとの排出量を可視化しており、コンプレッサーの排出削減に着手しているという。(画像提供:日崎工業)
小さな積み重ねが成果を生む、端材を活かした新ビジネスも
日崎工業は、京浜工業地帯の中核である神奈川県川崎市で金属加工業を営んでいる。ステンレスやアルミを材料に、イベント造作物や建築金物などをオーダーメイドで製造する金属加工技術が同社の強みだ。1958年の創業以来、金属加工一筋の事業を続けてきたが、新しい人材の定着に関して課題を感じていた。そこで、CEOの三瓶修氏は2013年、経営スタイルを「理念経営」にシフトした。
理念経営とは、会社が定めるビジョンや存在意義を重視する経営手法で、社員の判断や行動に一貫性を持たせることができるという。「会社全体の理念に加えて、部署ごとの理念も設けました。社員一人ひとりに、仕事を自分ごととしてとらえて取り組んでもらいたいと考えたからです。理念経営にシフトしてから、離職者は大幅に減りました」。三瓶氏は理念経営の一環で、省エネによるコスト削減にも力を入れた。「水銀灯からLED照明への更新工事などから始めた省エネ活動が、脱炭素化につながりました」と振り返る。
福島県にルーツを持つ三瓶氏は、東日本大震災の東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて、エネルギーを自給する重要性を強く感じていた。そんな時、当時契約していた新電力から、初期投資ゼロで太陽光発電設備を工場の屋根に設置する提案があったという。「新電力が設備や工事費用、メンテナンス費用を負担し、当社は太陽光発電の電気を自家消費した分だけサービス料を支払う仕組みで、無理なく導入することができました」と話す。
近年のパンデミックによって経済が停滞したことで、日崎工業は大きな打撃を受けた。そこで、エネルギーの自給というコンセプトをヒントに、新たなビジネスを開始した。自社の金属加工技術を活かし、加工過程で発生する金属の端材を使って、ランタンなどのアウトドア製品や、太陽光パネルを搭載したトレーラーハウスを製造。エンドユーザーへ直接販売し、新たな販路を開拓している。

ハイモンドは、日崎工業として初めての、エンドユーザーへ直接販売する「D to C」というビジネスモデルだ。川崎市のふるさと納税の返礼品にも選ばれている。(画像提供:日崎工業)
これまでの脱炭素化の取り組みを振り返って、三瓶氏は「CO2排出量を削減したからといって、即座に取引が増えるわけではないでしょう。しかし、省エネなど小さなことをコツコツ積み上げた効果は、結果としてコストにも跳ね返ってきます。これからの社会に必要とされる会社になるには、脱炭素化は1つの武器になると考えています」と力強く語った。
DATA

日崎工業株式会社
川崎市の臨海工業地帯に本社・工場を置く。板金加工技術によって、大型のモニュメントやオフィスビルの企業ロゴ、商業施設のフロアマップなど、街を支えるさまざまな金属製品を制作している。
取材・文:山下幸恵(office SOTO)
FACTORY JOURNAL vol.3(2024年秋号)より転載